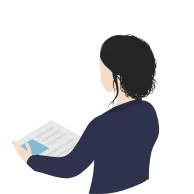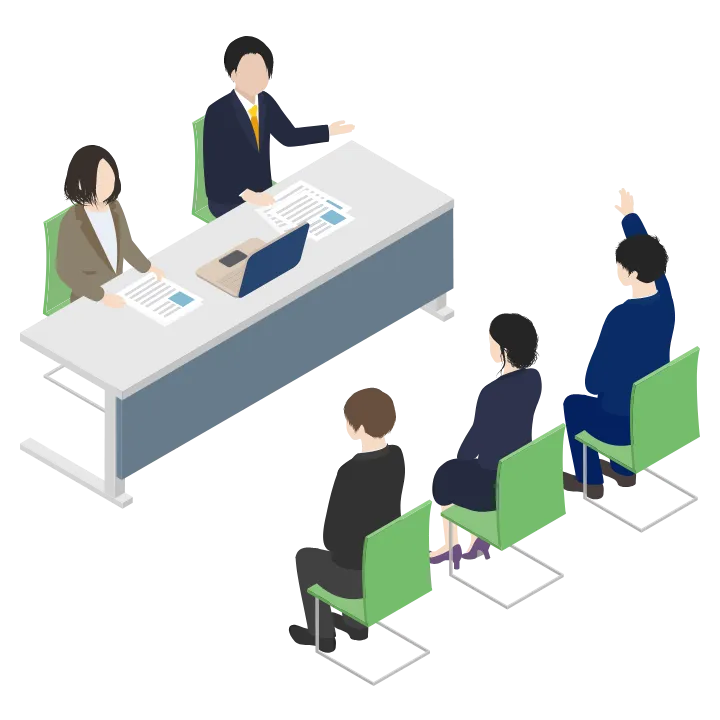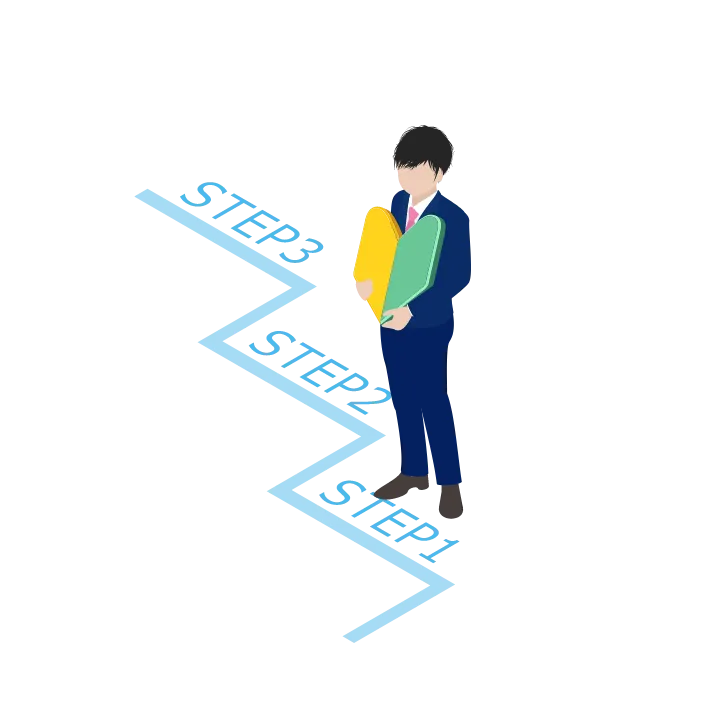YGPI
最適な職務やポジションに導く
こんなお悩みはありませんか?
- 配属先の決定が属人的な業務になっている
- 新入社員の定着と育成における課題
- データ活用の不足による配置・育成の最適化の遅れ
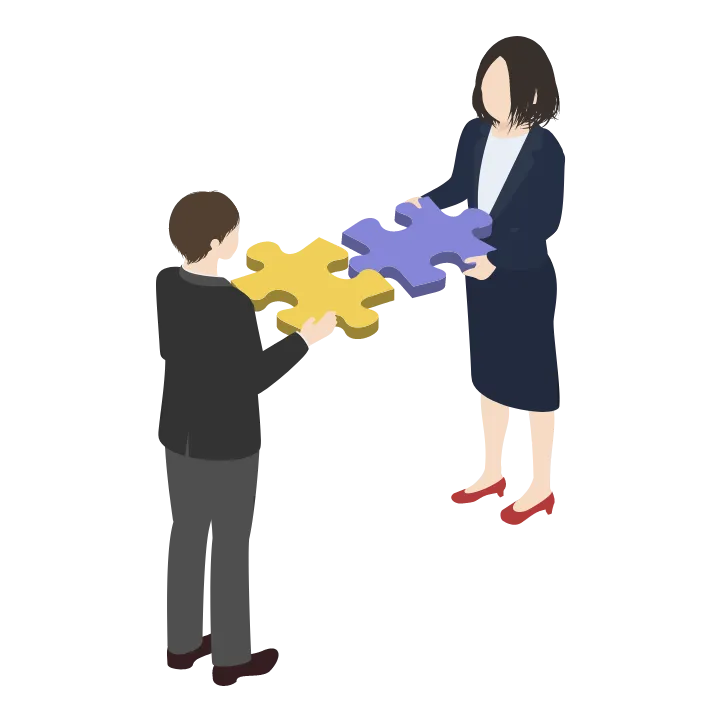
配置・配属の最適化で新入社員の適応をサポート
本人の特徴や希望を踏まえつつ、仕事内容や配属先の雰囲気、上司のタイプなど、多くの要素を考慮して配置・配属する必要がありますが、人事担当者の経験と勘で行っている場合が多いかと存じます。
しかし、新入社員、転職者の入社直後における円滑な適応がその後の活躍にもつながるため、配置・配属は大事な業務となります。YGPIは採用選考時の限られた情報に基づいて配置・配属を行う際に、本人の特性情報を基にしてどのような職務や組織に適応しやすいかを考慮しながら、配置・配属先を検討できるための重要な情報となります。

配置・配属先を検討する際には、経営計画や組織事情から、そもそもの配置・配属先候補の選択肢が限られる場合も多いかと存じます。
配属先の上司や同僚に新入社員のYGPIの結果をフィードバックすることで、新メンバーの特性を理解し、コミュニケーションのとり方や指導の仕方を工夫してもらうといった、定着・育成で活用されるケースも増えてきています。
若年層の人口減少や転職活動が活発になり、定着・活躍の重要度が増してきています。配置・配属や定着・育成支援以外でも、入社後のパフォーマンスデータとYGPIのデータを紐付けて分析することで、自社で活躍している社員の特徴から、必要な要員を検討するという活用方法があります。
こうした取り組みは以前から行われてきましたが、近年の傾向として見られるのは、分析手法の進化があります。人事データとアナリティクス技術を組み合わせることで、経営人事課題の解決を図る新しい取り組みが増えてきて、そうした場面でYGPIが注目されています。社内のデータベース上にYGPIのデータを取り込み、アナリティクスによって得られた知見を、施策に組み込んで活用されてきています。
Voice
事例紹介・お客様の声
Seminar
講習会も実施中!

お一人様から
何名様でもお受けできます
YGPIの基本を学べる講習会です。判定項目など判定表の見方を基礎から習得し、また受検者の傾向についてお伝えいたします。オンライン上または御社にて実施いたします。